またプレート損失は50Wとされていますが、どう見ても60W程度はありそうだと勝手に解釈して、やや控えめの(?)55Wによる動作でプレート電流は75mAとします。
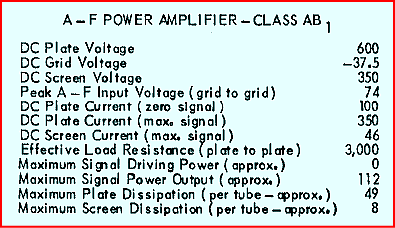
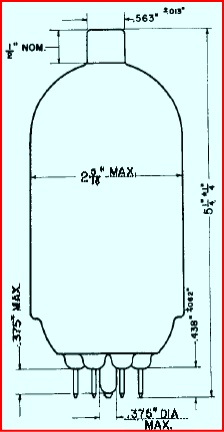
実測したカーブにロードラインを引くと下の図のようになります。あいかわらず予測ラインが多く、高圧3結を探求するには、そろそろマイナス100V以下のグリッド電圧を計測できるようにしたいものです。
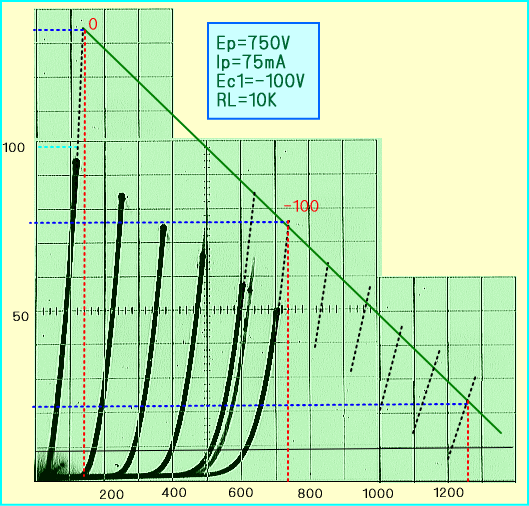
これをもとに回路図を構成してみました。電圧のかけかた以外はきわめて普通の無帰還3段増幅アンプです。
抵抗器も普通のカーボンで、電力のかかる部分はセメント抵抗、またカップリングコンデンサー以外は全てケミコンで、いわゆる「音の良いパーツ」はほとんど使っていません
出力トランスは14KΩですが2次側の16Ω端子に12Ω負荷をつないで、10KΩとして使っています。また初段管は直流点火で、誰がこれ作っても普通に残留雑音は0,5mV程度に収まります。
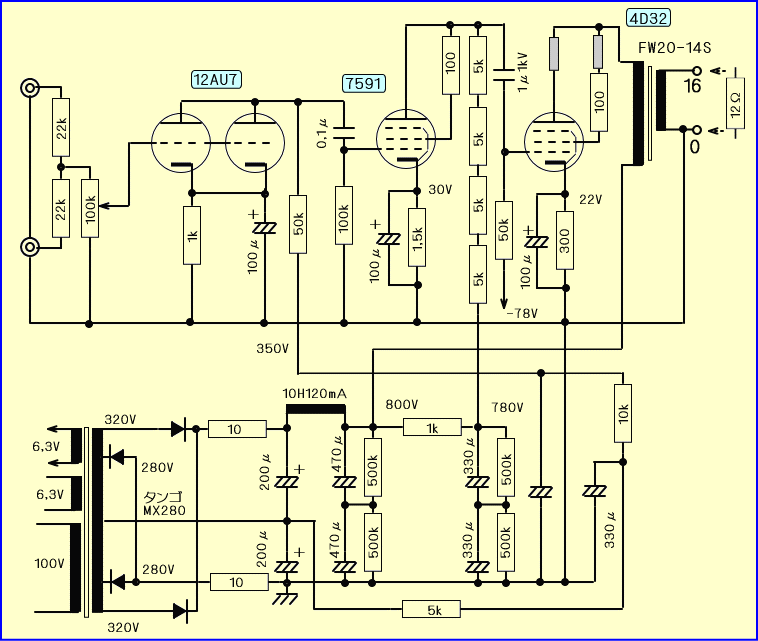
当初プレート損失を50W以下にして動作させたとこら、音が今ひとつだったため、試行錯誤の結果このような条件にたどり着きました。
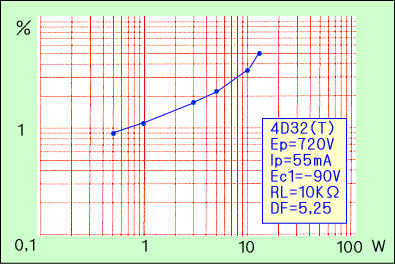
具体的には歪率計とオシロの波形による、最適と思える点を探し出していた結果、15Wで歪が3%を割った時、とても明るく軽く抜けの良い音がでて、少々おどろきました。
大げさな表現かもしれませんが、「探求者には褒美をとらそう。」という4D32の内なる声を聴いた感があります。うまく表現できませんが、森林を探検していたら御神木に出会えた、というような感じです。
右側にあるのがMJ誌に出ていた4D32ビーム管接続によるNFB4,8dB時の歪特性で、DFは3程度ですからHVTCがいかに興味深い動作かが、お分かりになると思います。。
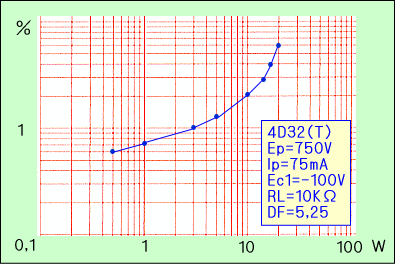
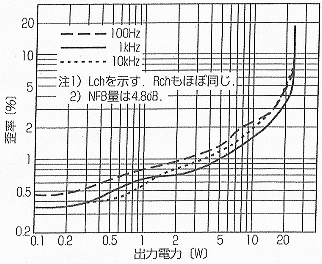
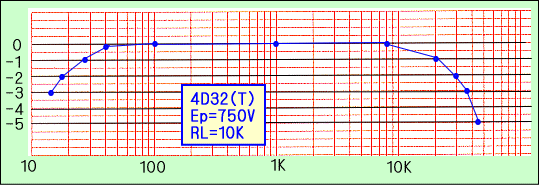
毎度書くようですが、高圧3結(HVTC)は新しい回路技術ではなく、真空管に対する新しい物理的解釈を意味します。そして歪率やダンピングファクターなどの点で、NFBや打消しなどをしないで、優れた値を出せます。
これを人に例えると、薬で健康を維持するのではなく、自身の免疫力で健康になるという感じに似ています。
次回は番外編で高圧ドライバーの紹介です。
、