メディアの発達で、ひとは1日中誰とも会話をする事無く暮らせますが、
実はメディアを構成する電子部品自体、非常に多くの科学者や物理学者が送るメッセージなのです。
この別冊では代表的な真空管とトランジスタのイメージを、感じていただきます。
「 真空管とトランジスタのイメージ 」
真空管もトランジスタも電圧や電流を増幅するためにあります。増幅とは小さな力で大きな動きをコントロールすることです。
例えば業務用水道管の水は勢いが強く、とても手で止められませんが、バルブ(蛇口)をつければ手で止められます。
通常バルブは手で操作しますが、これを水で操作できるようにしたら、大きな水の動きを小さな水の力でコントロールした、
つまり水の流れの増幅になります。
ちなみに真空管を英語で「バキュームチューブ」とは別に「バルブ」と呼ぶのは、こうした動作から来ているのです。
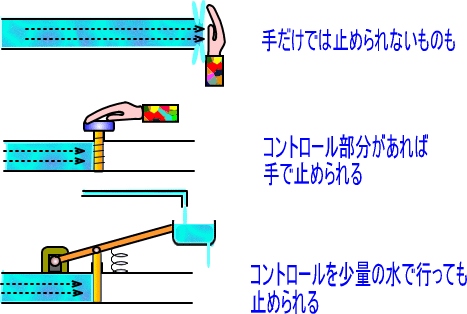
真空管やトランジスタも同じような機能があって、わずかな電気の変化で大きな電気の流れをコントロールできます。
また真空管よりトランジスタのほうが新しい電気素子という訳ではなく、真空管の実用化が思いのほか早かったため、
あっという間に普及してしまっただけで、両者のスタートはどちらが先とも言えません。
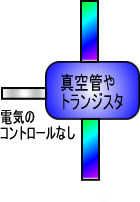

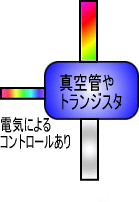
【2極管】
それでは、なぜこのような事ができるのか、その仕組みを見てみましょう。
真空管を見てみると、ガラスチューブの中に金属板で出来た電極が見えます。
これがプラスの電極でプレートといいます。
また、動作中の真空管は中心あたりに、煌々と光るヒーターが見えます。これがマイナスの電極でカソードといいます。
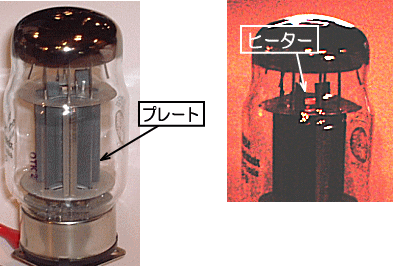
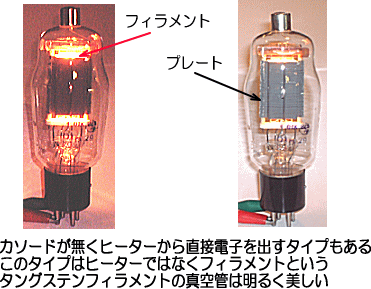
金属はもともと、たたいたり熱したりすると、その中から電子が飛び出しやすくなる性質があるので、
マイナスの電極を熱するため、ヒーターつまり電熱器が入っているのです。
この状態でプレートに電池のプラス、カソードに電池のマイナスをつなげると、熱せられたカソードの電子が、
プレートに飛び移ろうとします。これは静電気の働きによるものです。
ところが途中に空気の分子(酸素や窒素)があると、これがじゃまして効率よく飛び移れません。
また酸素はヒーターをどんどん酸化させて、燃やしてしまいます。
そこで全体をガラスチューブで覆い、中を真空にするのです。
これをプレートとカソードという2つの電極で出来た真空管、2極管といいます。
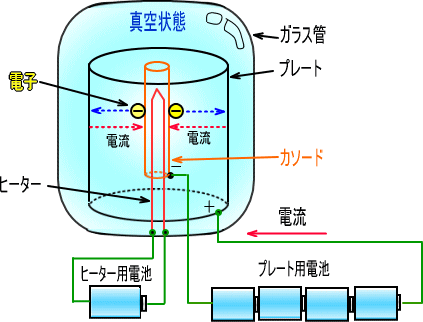
ところで上の図では、電流と逆方向に電子が移動しているように描かれていますが、これには訳があります。
電気の存在が発見された時「電流とはプラスの電気の粒がプラス側からマイナス側に流れること。」と考えられていました。
しかし物理学の発達により、「電流とはマイナスの電気の粒である電子がマイナス側からプラス側へ、流れていること。」
とわかったのです。
そこで両方の考え方をそのまま生かし、「電流が流れたときは、逆方向に電子流が流れていることになる。」
と考えることにしました。
例えて言えば、幸福が入ってくるのは、不幸が出てゆくのと同じだ、といった感じです。
一般に、電気を学ぶときは電流の考え方、物理や化学では電子流の考え方で、理解を深めてゆきます。
真空管の仕組みを物理的に理解するには、電子流の考え方で進めますが、
単なる電気の部品として理解するときは、電流の考え方で進めます。
真空管の特徴とは、カソードは加熱されているのにプレートは加熱されていないという点です。
そのためプレートとカソードに逆向きに電池をつないでも、プレートから電子がほとんど飛び出さないのです。
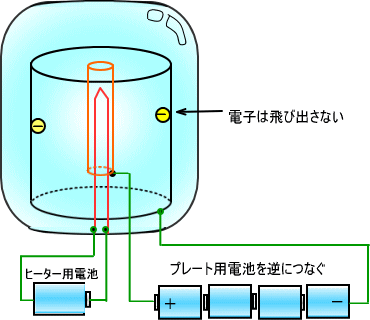
このように真空管は電気の一方通行を行い、これを整流といいます。
家庭のコンセントは100ボルトの電圧が来ていますが、電池のように、
どちらかがプラスで、どちらかがマイナスとはなっていません。
コンセントの電圧は交流といって、いつもプラスとマイナスが、波のように入れ替わっているのです。
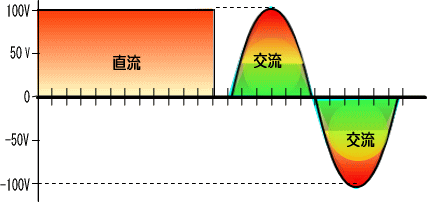
ところがテレビやパソコンなど、ほとんどの電子機器は、プラスマイナスが定まっている直流で動きます。
また交流のままでもよかった洗濯機や冷蔵庫も、中にコンピューターが組み入れられて、直流が必要となっています。
そんなとき整流が役に立ちます。整流では一方通行の特徴を利用して、プレートがプラスのときだけ電流を流す、
つまりいらないマイナス側を、ばっさり切り落とします。
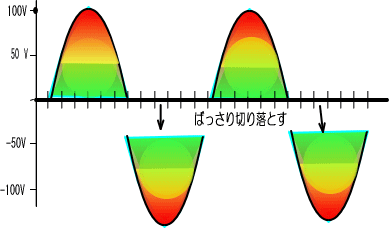
この波を、脈が打つような形から脈流といいます。このままでは直流とは違いすぎるので、
コンデンサという蓄電器でその間をうめます。
コンデンサは、自転車の空気入れについている空気室と同じで、空気入れを押していない時でも、
空気室に溜まった空気が隙間を埋めるように、脈流の隙間を埋めます。
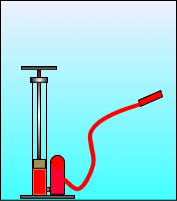
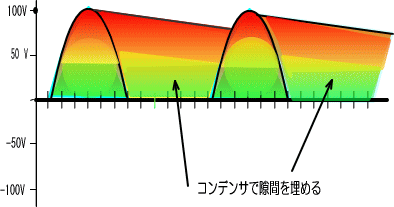
これでは電池など本物の直流とはちがいますが、この程度でも、がまんして働いてくれる電子機器は多くあります。
がまんならないという機器では、さらに電気的に処理をして直流に近づけます。
整流はトランジスタの原料である半導体でも作れますが、原理は大分ちがいます。
半導体とは電気を流す金属と、電気を流さないプラスチックなどとの中間にある物質です。
また整流作用では鉱石ラジオとして、半導体の方が真空管より先に実用化していました。
ところで、金属が重くプラスチックが軽い理由は、主に原子の重さによります。
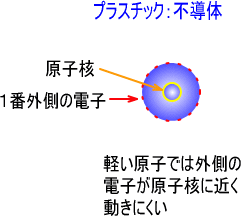
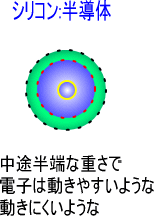
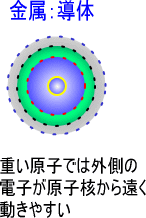
一方、半導体はその中間の重さで、電気を流すような流さないような、中途半端な性格を持ちます。
そこに注目して、人間が半導体に、親分と子分の関係を作ってやると、親分の命令は子分に伝わりますが、
その逆はできなくなります。
半導体の原料は地球上に大量にあるケイ素(シリコン)が代表です。。
半導体は、混ぜ物をして、電子が過剰気味と不足気味の結晶をつくり、二つを接合すると、
そこに原子レベルで電気の段差が出来ます。電子は高い所から低い方に落ちて移動できるのですが、
その逆は行けません。
こうして一方通行が出来ます。ただし、あまり勢いよく落ちると低いほうの床が壊れてしまいます。
落ちる勢いとは電圧の高さを意味し、内部を突き抜ける電子も出てきます。
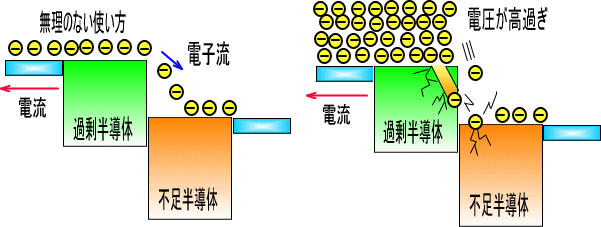
こうした理由から、初期のトランジスタは高い電圧に弱く、さらに電流の安定度も悪く、
トランジスタが真空管に取って代わる時代は来ないと、多くの人が感じたそうです。
当時は、シリコンの純度を上げるクリーンルームという概念も、まだ手探り状態でした。
ちなみにクリーンルームは、優れた半導体製造のためというよりも、
地球の年齢を知る研究において、鉛の純度を正確に計測するために生まれた技術です。
しかし真空管では、とても太刀打ち出来そうにない電子機器が登場しました。
それがABCマシンから始まった電子コンピューターです。
使用するのと同じ電力が必要でした。
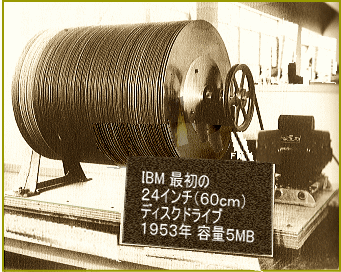
コンピューターも大きいが周辺機器も大きい
【3極管】
2極管はすばらしい発明でしたが、早々と特許がとられてしまったので、特許を逃れるため、
プレートとカソードの間にもう一つ別の電極をいれた3極管というものを考えた人がいました。
3つめの電極の意味は当初「これは2極管ではないから特許を侵害しない。」と言う程度のようだったのです。
しかし、この第3の電極こそが、増幅つまりコントロールを行うバルブ(蛇口)の意味を持っていたのでした。
第3の電極はプレートとカソードの間に置かれるので、板状では、電子の通行のジャマになってしまいます。
そこで電子がすり抜けられるよう、グリッド(格子)状の電極とし、この電極をグリッドと呼ぶことにしました。
グリッドにはカソードよりもさらにマイナスになるよう電池をつなぎます。
するとマイナス同士の静電気の反発で、電子はプレートに飛び移りにくくなります。
このグリッド電圧をバイアス電圧といいます。
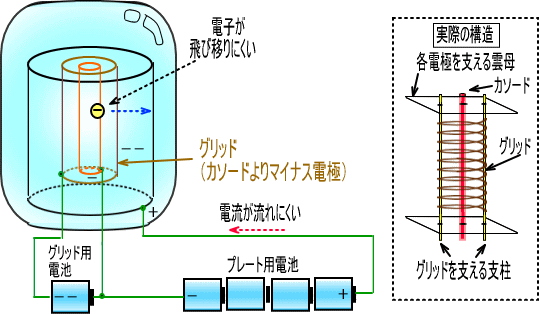
グリッドをさらにマイナスにする事を「バイアス電圧を深くする」といいます。
すると、ついに電子はカソードから出られなくなりますが、この状態をカットオフ状態といいます。
尚、グリッドは格子というよりコイル状になっています。またイラスト中ヒーターは省略しました。
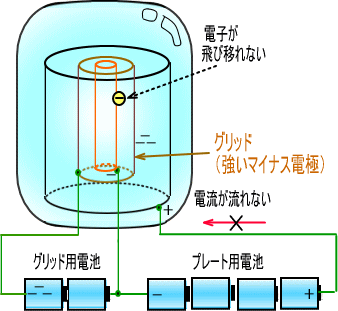

反対にバイアス電圧を浅くしてカソードと同じ電圧つまりゼロボルトにすると、電流が最大になります。
この状態を飽和状態といいます。
グリッドが丈夫に出来ている一部の真空管は、さらにプラスにすることも出来ますが、通常はゼロ止まりです。
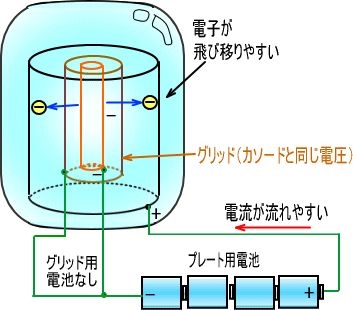
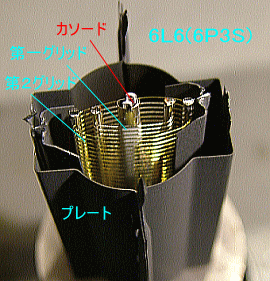
こうして出来た3極管は、少ないグリッド電圧の変化でプレート電流を大きく変化させ、
電気信号の増幅を行います。またカットオフと飽和状態は、電流を切ったりつないだりする
電子スイッチとして見ることも出来ます。
当然3極管のようなことを、半導体にもやらせようと考えた人たちがいました。
そうして出来たトランジスタには、真空管には出来ないことがあったのです。
トランジスタは、電子が過剰気味な半導体と不足気味な半導体の、サンドイッチ構造で作ります。
ところが、これには2種類の組み合わせがあって、それぞれは、コントロールする電圧のかけ方がまったく逆になるのです。
つまり、電子の流れをお堀でくい止め、時々お堀の底を「引き上げ」て、電子を通す方法と、
流れを塀(へい)でくい止め、時々塀を「引き下げ」て、電子を通す方法です。
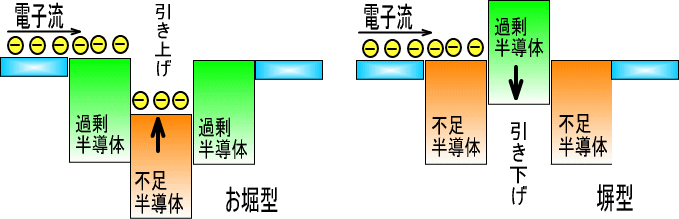
それぞれの用途は、お堀のほうは、プラスの電気用、
塀のほうはマイナスの電気用として便利に使い分けることができます。
さらに高い電圧や大きな電流にも強いトランジスタが続々開発され、ヒーター不要や小型などの特徴から、
ここに来て真空管としては、「おみごと!」と言わざるをえなかったのです。
こうして1970年ごろを境に、真空管は秋葉原から姿を消し始め、そのまま消滅するかにみえました。
真空管に見切りをつけて廃棄したパーツ屋のゴミ箱は、まさに宝の山で、多くのマニアがそれを拾っていました。
それを不快に思った店員が、鉄棒で真空管を潰し始めた時の歪んだ表情は、今でも悲しい思い出として残ります。
かつて一般家庭に、大量の真空管が入っていった時期があります。
それは東京オリンピックや皇太子妃ご成婚によって始まった、テレビの大量普及時代です。

さらにカラーテレビの普及で、様々な真空管が開発されましたが、
やがてそれらもブラウン管以外、全てトランジスタに代わりました。
そして次にやってきたオーディオブームも、主役は歪の少ないトランジスタになっていました。
歪を打ち消す負帰還という方式が、真空管よりもトランジスタに向いていたのです。
そんな時、ある電気関係の雑誌から、真空管アンプのブームが起きました。
電子部品である真空管がブームになるということは、もはや真空管の存在が実用品から
趣味の世界へ移ったことを意味しています。
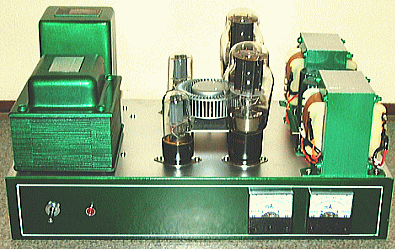
しかもその中心は1950年代以前の物が多く、懐古趣味のように思われていましたが、
これこそが、本来必要ないと思われていた、「アンプのキャラクター」を求める動きの始まりだったのです。
それまでアンプに求められる性能は、「無色透明」が原則でした。
余計なキャラクターは邪道だったのです。
同時期、日本人にも個性を尊重する時代が始まろうとしていました。
戦後の日本で、本格的に民主主義が定着し終えたと言われる時代です。
このようにして、ガラスチューブのかたちがボディラインのように、ヒーターが心の灯火のように、
さらに出てくる音が歌声のように例えられ、まさに真空管は人格を得たのでした。
真空管とトランジスタのレースは、半導体開発の遅れで、一時的な真空管のリードとなりました。
また第2次世界大戦により、実用化にメドがついている真空管が、優先的に開発されたことも、
真空管にとってラッキーだったと言えます。
しかし、もし真空管開発にも遅れが出ていたら、消費電力が少なく小型のトランジスタに開発資金が流れ、
特殊なものを除き、真空管の出番はほとんど無かったかもしれません。
一方トランジスタがいかに優秀になったとしても、部品同士を半田付けしている時のレース内容は
せいぜい徒歩と馬車の違い程度でした。
ところがモノリシックICの登場という画期的な出来事により、半導体はジェット機の如く、
あっという間にレース会場を飛び越えてしまったのです。
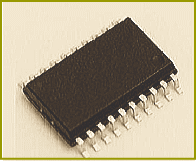
モノリシックICは、安価な抵抗器やコンデンサをも、超高価なシリコンウエハーで構成するという、
当時としては極めて馬鹿げた発想の産物だったため高価となり、当初全く売れませんでした。
しかし東西冷戦のミサイル関連と宇宙開発競争で、大量の国家予算がIC開発資金を潤し、
さらに価格を問わず、大量に軍部やNASAがそれらを買い上げたため、ICメーカーは急成長しました。
皮肉にも2次世界大戦が真空管を成長させ、東西冷戦が今日のコンピューター繁栄に役立ったのです。
.
